今、あなたは自分の人生に満足していますか?
もし、不満と感じているなら、その“生きづらさ”は、無意識のうちにあなた自身が選んでいるのかもしれません。

たとえば、職場でこんなことを思ったことはありませんか?
「もっと自分をわかってほしい」「あの人と働くのは苦手」「違う会社で働きたい」
――でも、アドラー心理学ではこう考えます。
「変化することが怖い」「現状維持の方が楽」
人はそんな思いから、つい“言い訳”を探してしまうのだと。
でも、それはあなたが悪いわけではありません。
今の社会は、他人の評価や周囲の目にとても敏感な時代です。
そんな環境の中で、自分らしさを失ってしまうのは自然なこと。
そんなときこそ手に取ってほしいのが、アドラー心理学をベースにしたベストセラー**『嫌われる勇気』**です。
この本は、過去の経験やトラウマに縛られず「いま、ここ」に集中して生きるためのヒントをくれます。
この記事では、その中でも特に実践的な3つの視点――
「原因論と目的論」「すべての悩みは人間関係」「課題の分離」
これらにフォーカスし、他人の目から解放され、自分らしく生きるためのヒントをお届けします。
本の内容
まず誤解してほしくないのは、タイトルにある『嫌われる勇気』という言葉。
決して「わざわざ嫌われにいこう!」という内容ではありません。
本書が伝える“嫌われる勇気”とは、他人の目や評価を恐れずに、自分の信念を行動に移す勇気のこと。
たとえその結果、誰かに嫌われるリスクがあったとしても、それはあなた自分自身の課題ではないと語られています。

そして本書の核心のひとつが、「すべての悩みは対人関係の悩みである」という考え。
人はひとりで悩むことはありません。容姿やお金、暮らしなど、自分と誰かを比較することで劣等感や不安が生まれるのです。
ただし、他人と比較すること自体が悪いわけではありません。
本書が伝えているのは、相手を“敵”ではなく、共に成長していく“仲間”として捉えることが大切だということです。
また、「期待に応えたい」「褒められたい」といった縦の関係ではなく、
お互いを尊重し合う“横の関係”を意識することで、
人との関わり方を見直し、自分自身を取り戻すためのヒントが得られると説いています。
著者情報
岸見 一郎(きしみ・いちろう)
哲学者。1956年京都府生まれ。専門は西洋哲学、とくにプラトン哲学。長年にわたりアドラー心理学の研究・普及に努め、哲学と心理学の橋渡し役としても知られる。実践的かつ日常に根ざしたアドラー心理学の解説に定評があり、カウンセリングや講演活動も行っている。
古賀 史健(こが・ふみたけ)
編集者・ライター。1973年福岡県生まれ。数多くのベストセラーを手がけるブックライターとして活躍し、専門知識を平易な言葉で伝える構成力に定評がある。本書では“青年と哲人の対話”という独自の形式で、アドラーの思想をストーリー仕立てに再構築。難解な理論を誰にでもわかりやすく届けることに成功している。
アルフレッド・アドラーについて
アルフレッド・アドラー(Alfred Adler/1870–1937)
オーストリア出身の精神科医・心理学者。フロイトやユングと並ぶ、現代心理学の礎を築いた人物の一人です。かつてはフロイトと共に精神分析を研究していましたが、人間を“性”ではなく“社会との関わり”の中で理解しようとする姿勢から袂を分かち、独自の心理学を展開しました。
アドラーが提唱した**「個人心理学」**は、「人は劣等感をバネに成長し、他者とのつながりの中で生きていく存在である」とする考えが核にあります。
その教えは「目的論」「自己決定性」「共同体感覚」「課題の分離」などのキーワードで語られ、現代の自己啓発や教育、対人関係論にも大きな影響を与え続けています。
「人は変われる」という前提に立ち、他者に依存しない“自立した人生”を後押しするアドラーの哲学は、今なお多くの人に支持され、現代社会の悩みに光をあてるヒントとなっています。
自分らしく生きるための3つのポイント
①「原因論」と「目的論」を知る

「過去のせいで変われない」は、本当?
「あのとき親に厳しく育てられたから、人間関係が苦手になった」
「失敗した経験があるから、新しいことに挑戦できない」――
こんなふうに、私たちはつい“過去の出来事”を言い訳に、今の自分を説明してしまいがちです。
このような考え方は、心理学で**「原因論」**と呼ばれます。
つまり、「今の自分は、過去によってつくられた」という見方です。
でもアドラーは、この原因論を明確に否定します。
代わりに重視するのが、**「目的論」**という考え方。
目的論では、私たちの行動は「過去に縛られている」のではなく、
**「自分の目的に沿って、いまの行動を選んでいる」**と考えます。
たとえば――
「人間関係が苦手」なのは、「人と関わり、嫌われるのが怖いから距離を取っている」
つまり、“傷つかないため”という目的があるという見方です。
過去を理由にして行動を止めるのか。
それとも、自分の内側にある“目的”を見つけて、一歩踏み出すのか。
変化の鍵は、「過去」ではなく「いま、何のためにその行動をしているのか」を見つめること。
目的論という新しい視点を持つことが、自分らしく生きるためのスタートになります。
②承認欲求を捨てる
「すべての悩みは、対人関係の悩みである」

どんな悩みも、突き詰めれば“対人関係”に行き着く。
仕事のストレス、家族との不和、自信のなさ…。
一見バラバラに見える悩みも、アドラー心理学はこう断言します。
たとえば、「自信がない」と感じるとき。
それは、多くの場合、“他人と比べて自分は劣っている”という感覚から生まれています。
そして劣等感を抱えた私たちは、いつの間にかこう思うようになります。
「誰かに認めてほしい」「もっと評価されたい」と――
これが、承認欲求です。
承認欲求とは、「他人からの評価や期待に応えようとする気持ち」。
マズローの欲求5段階説でも上位に位置づけられる、根深く強い欲求です。
でもアドラーは、こう考えます。
「承認欲求があるから、人は不自由になる」
他人の期待に応えようとすればするほど、
自分の本音や、本当にやりたいことは後回しになってしまう。
それはつまり――
**「自分の人生を、他人の手に委ねてしまうこと」**でもあるのです。
でも、こう考えてみてください。
悩みの多くが“対人関係の中で生まれた感情”だと気づくだけで、
少しだけ肩の力が抜ける気がしませんか?
まずは、自分の悩みが「誰の目」を気にして生まれたものなのかを見つめてみること。
そして、他人を満たすのではなく、
「自分はどう生きたいのか?」を問い直すこと。
自分に嘘をつくのをやめること。
その小さな視点の転換が、
他人の評価に縛られず、「自分らしく生きる」ための鍵となります。
③課題を分離する
「あの人を変えたい」「世の中に変わってほしい」は、誰の課題?
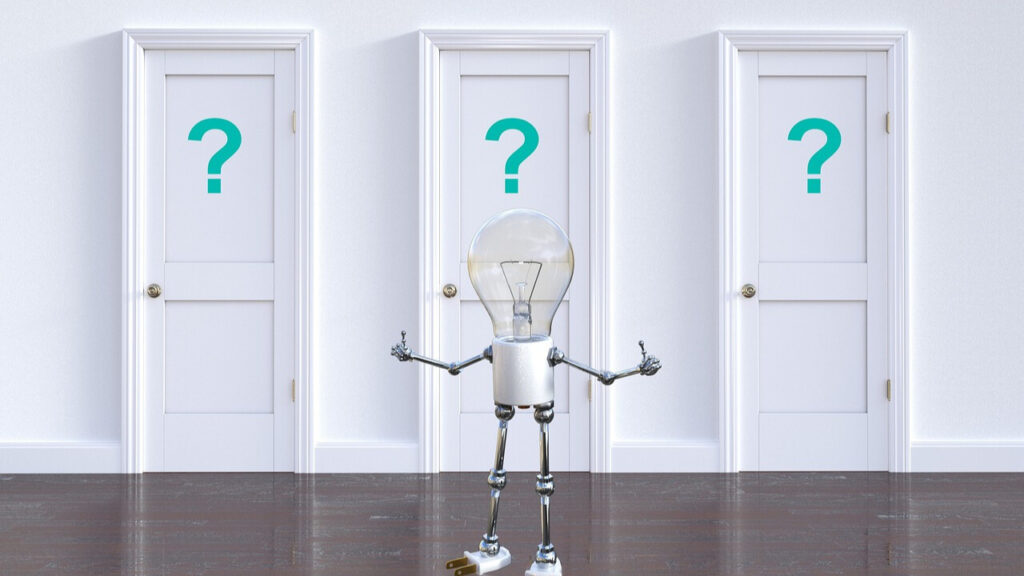
「もっとわかってほしい」
「生きにくい世の中だ」
そんなふうに、他人や環境にイライラした経験は、誰にでもあるはずです。
そんなとき、アドラー心理学が教えてくれるのが――
**「課題の分離」**という考え方です。
つまり、「それは誰の課題か?」を見極めること。
たとえば、こんな言葉があります。
「馬を水辺に連れて行くことはできても、水を飲ませることはできない」
馬を水辺まで連れていくことが飼い主の課題です。しかし、水を飲むかどうかは馬の課題です。
他人がどう行動するかはその人次第、その人の課題です。
自分がコントロールできるのは、“自分の行動”だけです。
だからこそ、他者を変えようとするのではなく、
自分に変えれるもの“自分の課題”に集中すること。
コントロールできない他人の課題まで背負い込めば、
人間関係のストレスやモヤモヤは増える一方です。
他人の課題を手放し、自分の人生に集中する――
それこそが、自分らしく自由に生きるための自分の課題なのです。
まとめ
✅ 言い訳を探そうとせず、本当のやるべきことに目を向ける
✅ 他人に認められようとしない
✅ 自分の力で変えることができるもの(=自分の課題)だけに集中すること

『嫌われる勇気』は、自己成長や人間関係の悩みに向き合うための“哲学的ガイド”のような一冊です。
過去や未来を理由にするのではなく、「いま、ここ」をどう生きるかにフォーカスすることで、
人は自分の意志で人生を切り拓けるのだと教えてくれます。
その中核にあるのが「目的論」という考え方。
自分の行動には、必ず“何かしらの目的”があるとする視点です。
たとえば、「怒り」や「不安」も、実はその背後に目的がある――
このことに気づくことで、本来の進むべき道が見えてくるはずです。
さらに、「課題の分離」というアドラーの実践的な視点を取り入れることで、
人間関係のストレスも驚くほど軽くなります。
他人の課題に介入せず、自分の課題には責任を持つ。
その境界線を意識することで、自然と健全な“横の関係”が築けるようになるのです。
この考え方は、SNSや評価社会のなかでつい「人の目」に縛られてしまう現代人にこそ必要なもの。
たとえ完璧にできなくても、「これは自分の課題か?」「いまの行動の目的は何か?」と
自分に問い直すだけで、少しずつ心が整い、自分のやるべき行動が見えてくるようになります。
もしあなたが、他人の目や人間関係に悩まず、
**「本当の意味で、自分らしく生きていきたい」**と思うなら――
この一冊は、きっとその一歩を踏み出すための力をくれるはずです。
書籍情報
【書籍名】嫌われる勇気 自己啓発の源流「アドラー」の教え
【著者名】岸見 一郎(きしみ・いちろう)古賀 史健(こが・ふみたけ)
【出版社】ダイヤモンド社
【出版日】2013/12/13
【項数】296ページ
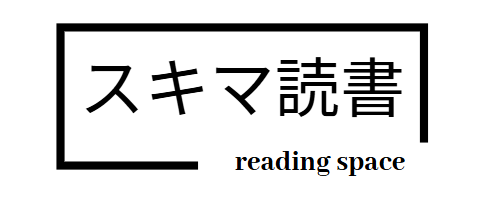
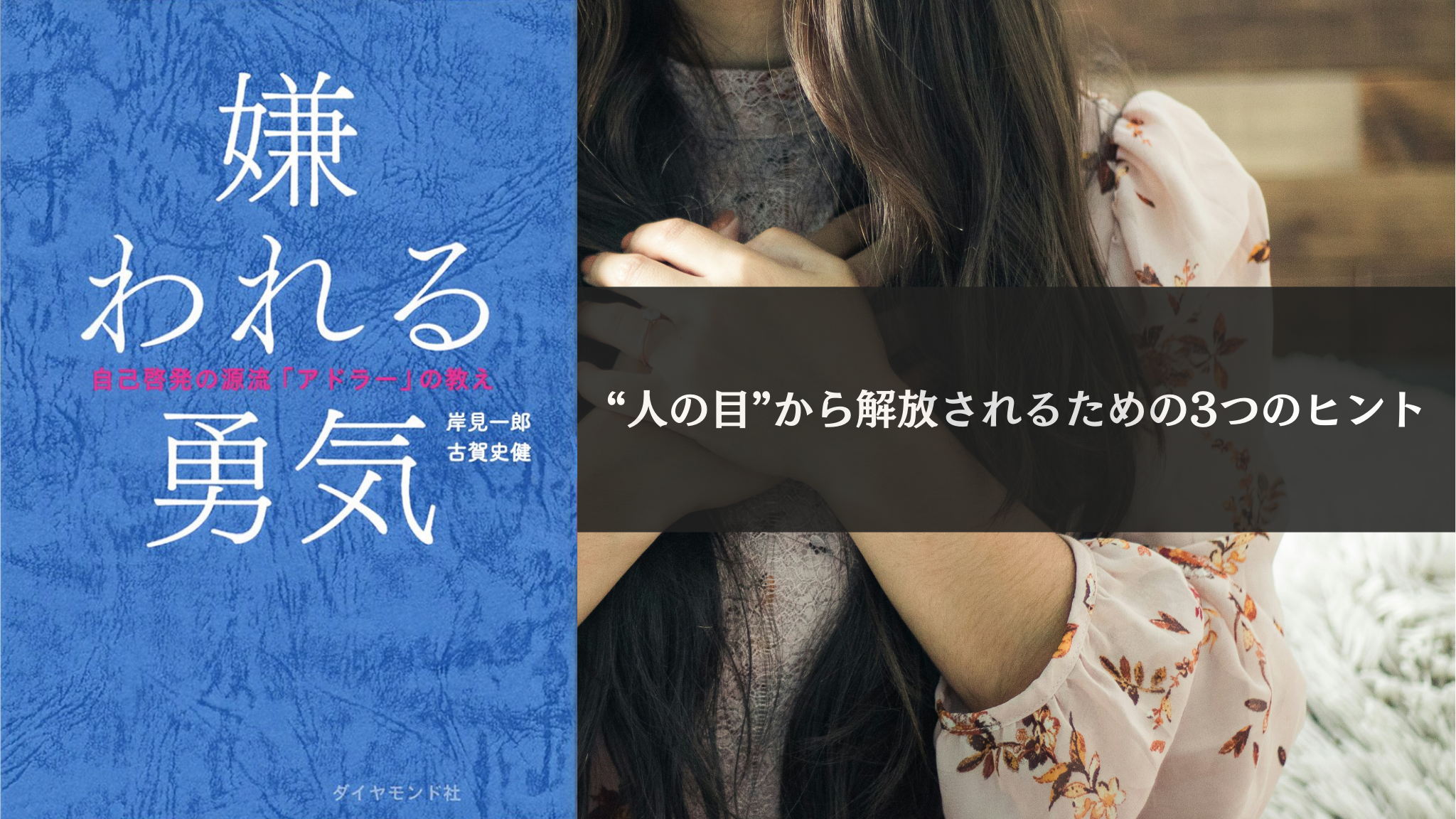

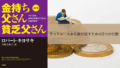
コメント