
結果を出す人と出せない人の違いはどこにあるのか?
プロゲーマー・梅原大吾氏が語る”勝ち続ける”ための思考法は、ゲームに限らず、仕事や人生においても応用できるヒントに満ちていました。
まず、「勝つこと」と「勝ち続けること」は本質的には違うものだと語られています。
本書に書かれていることは、ただ勝つのではなく、「勝ち続ける」ことに主眼を置いているという点である。
なぜ、「勝つ方法」ではなく「勝ち続ける方法」なのか? 両者は似て非なるもので、時としては相反するほどに大きな隔たりを見せる。
「勝つ」という言葉は、「結果を出す」と言い換えることでよりイメージしやすくなるかもしれない。「結果を出す」ことと「結果を出し続ける」ことは根本的に性質が異なる。
結論から言えば、勝つことに執着している人間は、勝ち続けることができないということ(~後略~)
梅原大吾. 勝ち続ける意志力 世界一プロ・ゲーマーの「仕事術」 (小学館101新書) (p.8). 小学館. Kindle 版.より
言い換えるなら、「短期的な結果」よりも「長期的な成長」、「周りの評価」よりも「自分自身と向き合うこと」が長い目で見ると大切だ、ということです。
では、梅原さんが長年にわたり”勝ち続けてきた”背景には、どんな考え方や取り組み方があったのでしょうか?
その核心を、この記事で掘り下げていきます。
本の内容

本書は、タイトルにもあるように「勝ち続ける」ことに焦点を当てています。
短期的な勝利ではなく、長期的に勝ち続けるためには、成長し続けることが不可欠だと梅原氏は説きます。そのためには、継続的な努力と、それを支える精神のバランスが重要だということ。
ゲームの世界では前例のない道を歩んできた梅原さんは、数々の苦難に直面しました。時には「この道は間違いだったのではないか…」と迷い、ゲームから離れた時期もあったそうです。それでも再び戻り、自分自身と向き合いながら前に進み続けました。
幼少期からプロゲーマーになるまでの彼の思考や取り組み方には、ゲームに限らず、仕事や日常生活、さらには「生きること」の本質に触れるヒントが詰まっています。
周りの評価にとらわれず、ひたすら自分自身と向き合い続けた結果、彼は世界一に到達しました。
“結果は後からついてくる” ― その言葉を、彼はまさに体現しているのです。
目の前のできることにのみ集中していれば、ふとしたときに信じられない高みにいることに気づく日が来るだろう。
梅原大吾. 勝ち続ける意志力 世界一プロ・ゲーマーの「仕事術」 (小学館101新書) (p.143). 小学館. Kindle 版.より
著者情報
日本人初のプロゲーマーとして知られ、2D対戦格闘ゲームの分野で国際的に名を馳せる存在。
特に『ストリートファイター』シリーズの活躍が際立っており、今なおトップレベルを維持し続けています。
そのプレイスタイルや功績から、「ウメハラ」「The Beast」「王」などの愛称で親しまれ、eスポーツ業界への貢献は計り知れません。
選手としてだけでなく、プロゲーマーという道を切り開き、”勝ち続ける”思考を多くの人に示し続ける存在でもあります。
1981年青森生まれ。日本人で初めて〝プロ・ゲーマー〟という職種を築いたプロ格闘ゲーマー。年、17歳にして世界一の称号を獲得。
一時ゲームから離れていた3年間で、麻雀の世界でもトップレベルとなる。
年4月、アメリカの企業とプロ契約を締結。同8月「世界で最も長く賞金を稼いでいるプロ・ゲーマー」としてギネスが認定。「背水の逆転劇」と呼ばれる試合の動画再生回数は全世界で2000万回超。その勝負哲学は、ゲーム以外の世界からも賞賛を受けている。
梅原大吾. 勝ち続ける意志力 世界一プロ・ゲーマーの「仕事術」 (小学館101新書) (p.177). 小学館. Kindle 版.より
YouTube
X(旧Twitter)
Twitch
成長し続けるための3つのポイント
① 変化し続ける:新しい挑戦が成長を生む

成長し続けるために欠かせないのが 「意識的な変化」 です。
同じやり方、同じ環境に留まり続けると、慣れや安心感に支配されてしまい、いつしか成長は止まってしまいます。
梅原氏も、 「昨日と同じ自分」で終わらせない ために、少しの変化を試し続けることを大切にしています。
・いつもと違うアプローチを一つ加えてみる
・新しい戦法や考え方を取り入れてみる
・成功、失敗関係なく、その経験を”変化の材料”にする
変化は怖いもの。でも、変わり続けることをやめた瞬間、停滞が始まる。だからこそ、 あえて変わり続ける”意志”を持つ ことが重要なのです。
いきなり大きな変化を起こそうとすると、目の前の壁の高さに尻込みしてしまうかもしれません。
まずは小さな変化から、 「昨日より今日、今日より明日」 と、自分を更新し続けることが成長を促すのです。
まずは目の前の5段を登ってみればいい。次にもう5段が見えたら、また登ればいい。
そうやって毎日5段ずつ登っていけば、500段登るのもそれほど苦痛に感じないだろう。最初から500段登るぞと熱くなると、往々にしてあとが続かない。
梅原大吾. 勝ち続ける意志力 世界一プロ・ゲーマーの「仕事術」 (小学館101新書) (p.143). 小学館. Kindle 版.より
②精神バランス:努力を続けるために

成長を続けるためには、努力を支える「精神的なバランス」が欠かせません。
結果に一喜一憂せず、感情に振り回されない強さが大切です。勝っても浮かれず、負けても落ち込みすぎず、事実を冷静に受け止めて分析を続けることが「勝ち続ける」ための鍵となります。
また、満足しかけているときこそ、自分に鞭を打ち、目的と目標を再確認することが必要です。
反対に、心が弱っているときは無理をせず、回復を図ることも重要です。梅原さんが介護を経験した際に学んだように、「人と関わり、人のために何かをする」ことが、心を立て直すきっかけになることもあります。ときには勝負からいったん距離を置く勇気も必要です。
さらに、体を動かすこともリフレッシュには効果的です。梅原さんが散歩配信をしているように、シンプルな行動でも心身を整える力があります。
③考える力:結果を”結果のまま”終わらせない

勝った、負けた――その結果を「ただの結果」として終わらせてしまったら、そこで成長は止まります。
梅原さんが大切にしているのは、 「なぜ勝てたのか」「なぜ負けたのか」 を考え続ける姿勢です。
・あの人とこの人の違いは何だろう?
・自分の良かったところ、悪かったところは?
・もし別のやり方を試していたらどうなっていただろう?
そうやって視点を変えながら、 結果を材料にして思考を重ねる ――その積み重ねが「次の成長」につながるのです。
答えが見つからないこともあるでしょう。でも、 考え抜くことで見えてくるもの が必ずある。
その「考える習慣」こそが、勝ち続けるための土台になるのです。
まとめ
✅ 変化し続けること
→ 意識的に新しいことに挑戦することで成長を促す。
✅ 精神的なバランスを保つ
→ 結果に一喜一憂せず、満足せず、落ち込まず。目的を見つめ直し、歩みを止めずに進み続ける。
✅ 考える力を鍛える
→ 結果をそのまま終わらせず、「なぜ勝てたのか?なぜ負けたのか?」徹底的に思考・分析する。

『勝ち続ける意志力』を読んで感じたのは、“成長し続けること” の大切さです。
チャレンジ精神を持ち、変化し続けること、考え続けること――そして、それらを支える精神力。
結果だけに囚われず、本来の目的を見失わなければ、たとえ歩みが遅くても確実に前に進めるはずです。
本書を通して特に印象的なのは、梅原さんの言葉が持つ “納得させる力” です。
その理由は、すべてが 実体験 から生まれた言葉だからだと思います。
成功談だけではなく、苦悩や挫折をどう乗り越えたのか まで語られているからこそ、読者の心に深く響くのだと感じました。
さらに、配信などでの発言を見ていても、梅原さんが 常識や周りの評価に流されず、自分自身ととことん向き合い続けている ことが伝わってきます。
その徹底した思考力や分析力こそが、彼の言葉の説得力を支える土台になっているのでしょう。
「才能すらなぎ倒す努力」という表現に象徴されるように、”才能がないから諦める”のではなく、”どうやって勝つか” を考え続ける姿勢。
この姿勢そのものが、梅原さんを突き動かし続ける “強さの本質” だと改めて感じました。
そして、本書を読み終えた今、改めて気づかされたのが “読書の本当の価値” です。
成功談を追いかけるのではなく、「問題や悩みにどう向き合い、どう乗り越えたのか」 という部分に注目することで、得られる学びの深さがまったく違ってきます。
この本には、“本質的な学び” が詰まっています。
ゲームに限らず、「成長し続ける」 ためのヒントが欲しい人にこそ、心からおすすめしたい一冊です。
書籍情報
【書籍名】 勝ち続ける意志力
【著者名】 梅原 大吾
【出版社】 小学館
【出版日】 2012/4/2
【項数】 256ページ
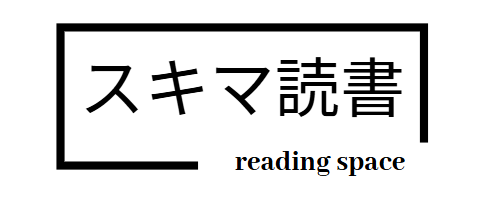



コメント