『孫子の兵法』は、単なる戦争論を超え、現代のビジネス戦略や自己成長にも応用できる古典として、ビル・ゲイツや孫正義など、多くの成功者に愛読されています。

本書を通じて学べるのは、「戦わずして勝つ」ための合理的な思考と、「勝つべくして勝つ」ための戦略です。
現代社会で例えるなら「戦う=競う」「勝つ=結果を出す」と言い変えられるでしょう。
本記事では、孫子のエッセンスを要約し、個人的に学んだポイントとともに、その活用の可能性について考察します。自分の課題や悩みを「自分ごと」の「向かうべき相手」として捉え、どうにか改善したいと感じている人にぴったりの一冊です。
本の内容

『孫子の兵法』は全13篇にわたり、戦争における基本原則や戦略の立て方、組織の運営法について論じています。本書では、歴史上の出来事や現代社会における具体例を交えながら、これらの戦略をわかりやすく解説しています。
1.始計篇(しけいへん)
事前の計画と勝算を見極めることが重要。勝てる見込みがないなら戦わない。
2.作戦篇(さくせんへん)
戦いは短期決戦が理想。長引くと消耗戦になり、不利になる。無駄な消費を抑えよ。
3.謀攻篇(ぼうこうへん)
戦わずして勝つのが最上の戦略。敵の意図を見抜き、有利に立ち回る。「彼を知り己を知れば百戦危うからず」。
4.軍形篇(ぐんけいへん)
こちらが不利なときは守りを固め、有利な状況になるまで待つ。戦いは選んで行うべし。
5.兵勢篇(へいせいへん)
個の力ではなく集団の力を活かすこと。正攻法(正)と奇策(奇)の両方を組み合わせるのが鍵。
6.虚実篇(きょじつへん)
兵の形は水のように変幻自在であるべき。臨機応変に動き、相手の弱点を突く。「四方を守れば四方が手薄になる」「一点集中」。
7.軍争篇(ぐんそうへん)
「迂直の計」──遠回りが結果的に近道になることもある。風林火山「疾きこと風の如し、徐(しず)かなること林の如し、侵略すること火の如し、動かざること山の如し」。
8.九変篇(きゅうへんへん)
状況に応じた柔軟な判断が求められる。バランス感覚を持ち、利益と損失を冷静に考える。
9.行軍篇(こうぐんへん)
目の前の現象にはすべて理由がある。観察を怠らず、敵の動きや地形から情報を読み取れ。
10.地形篇(ちけいへん)
地形は兵の味方。環境を把握し、戦略的に活用することで勝率を高められる。
11.九地篇(きゅうちへん)
追い込まれたときこそ本当の力が発揮される。「呉越同舟」「背水の陣」──極限状態では個と集団の力が最大化する。
12.火攻篇(かこうへん)
目的を見失わず、感情に流されず戦うことが大切。合理的な判断を最優先せよ。
13.用間篇(ようかんへん)
情報戦が勝敗を分ける。情報収集は最優先事項。専門家や内部情報をうまく活用することが重要。
孫子の兵法の凄さは、戦争だけでなく、ビジネスや日常生活にも応用できる点です。特に以下の点が現代社会においても重要だといえる。
・事前準備と戦略的思考(始計篇) → 無計画に動かず、勝算を見極めてから行動する。
・交渉力と問題解決力(謀攻篇) → 争わずに勝つ方法を考える。
・柔軟な対応力と適切なタイミング(軍形篇・兵勢篇) → 流れを見極め、最適なタイミングで動く。
・資源の活用と立ち回り(地形篇) → 自分に合った環境を選び、有利に動く。
・情報収集と分析の力(用間篇) → 情報を制する者が成功を掴む。
これらの考え方を意識することで、日々の判断力を養い、さまざまな場面、特にビジネスや競技の世界で実践的に活用することができます。孫子の兵法は、単なる軍事戦略の書ではなく、現代社会を生き抜くための知恵の宝庫といえるでしょう。
著者情報
守屋 洋(もりや・ひろし)
1932年宮城県生まれ。東京都立大学中国文学科修士課程修了。
現在、中国文学の第一人者として著述、講演等で活躍中。
主な著書に『兵法三十六計』『「孫子の兵法」がわかる本」『この一冊で「三国志」英雄のすべてがわかる!』、監修に『中国古典「一日一話」』『[図説]三国志がよくわかる事典』『「三国志」男の頭の使い方』『「孫子の兵法」の使い方』(以上三笠書房刊)など多数ある。
守屋 洋. 孫子の兵法―――考え抜かれた「人生戦略の書」の読み方 (知的生きかた文庫) (p.193). 三笠書房. Kindle 版.より
孫氏から学ぶ勝負のポイント3選
① 相手と自分を分析する|「彼を知り己を知れば百戦して殆うからず」

孫子の代表的な教えのひとつに、「彼を知り己を知れば百戦して殆うからず」という言葉があります。
これは、自分の長所・短所を理解し、相手の戦略や強み・弱みを把握することで、無謀な戦いを避け、負けない方法を見つけられるという考えです。
この考えは、ビジネスでも自己成長でも重要です。例えば、競合分析を怠らず、自社の強みを活かせる市場を選ぶこと。あるいは、自己分析を通じて、自分に合ったキャリア戦略を立てること。相手と自分のデータを見える化して客観的判断することが、成功への第一歩となるでしょう。
② 環境を利用する|「地形は兵の助けなり」

孫子は、戦いにおいて「地形」が重要であると説きます。
地形とは単なる物理的な地勢だけでなく、「状況」や「環境」全般を指します。つまり、戦いは人の力だけではなく、環境を味方につけることが勝敗を左右するのです。
現代に置き換えれば、ビジネスであれば市場環境の分析、キャリアでは自分が活躍しやすい環境を見極めることが大切です。例えば、成長産業に身を置けば努力が実りやすく、逆に衰退産業ではどれだけ頑張っても成果が出にくい。環境選びの重要性を改めて考えさせられました。
③ 変化に対応する柔軟性|「風林火山」

「疾きこと風の如く、徐(しず)かなること林の如く、侵略すること火の如く、動かざること山の如し」
甲斐の武田信玄が孫氏の兵法「疾きこと風のごとく、徐かなること林のごとく……」から「風林火山」の四文字をとって旗印としたことは広く知られています。
この「風林火山」は、状況に応じた動き方を示す有名な戦略です。
これは、現代のビジネスや個人の挑戦にも応用できる考え方です。例えば、新しい情報にアンテナを立て先手を打つ(風)、日々の努力は続けて実力をつけておく(林)、チャンスがあれば結果に繋げる(火)、そして状況が悪いときは無理をせず耐えて状況を分析する(山)。このように、変化する環境に適応しながら、臨機応変に最適な判断を下すことが求められるのです。
まとめ
✅ 目的やリスクを考えて、無駄な衝突を避ける
✅ 感情で動かず、冷静に「勝てるかどうか」を見極めて行動する
✅ 客観的な判断で自分と相手の戦力を見える化して分析する
✅ 環境の変化を察知し、環境に適応する
✅ 目の前の勝利より「その先」の損得まで見据えた思考が大切

孫子の兵法は、戦争という極限状況で生まれた戦略論ですが、その考え方は現代にも十分通用します。特に、人間の分析・環境適応・柔軟な思考という点は、仕事や人生においても活かせる教えでした。
一方で、その合理性ゆえに、「人間的な温かみがない」「倫理的にどうなのか」と感じる部分もありました。例えば、孫武が愛姫たちを処刑する逸話や、情報戦における徹底した非情さなどです。また、成功者の多くが孫子を愛読しているとはいえ、国家戦略レベルでの活用には賛同しかねる部分もあります。
しかし、個人の目標達成や自己成長、組織内での戦略といった限定的な範囲であれば、孫子の知恵は有効に活用できるでしょう。重要なのは、「そのまま実践する」のではなく、「現代の価値観や倫理観とすり合わせながら応用する」ことです。
孫子の兵法を単なる戦争論としてではなく、人間理解や組織の論理、自己成長や戦略的思考のツールとして活かす視点を持てば、新たな学びが得られるかもしれません。
書籍情報
【書籍名】孫子の兵法 考え抜かれた「人生戦略の書」の読み方
【著者名】守屋 洋
【出版社】三笠書房
【出版日】1984/1/1
【項数】274ページ
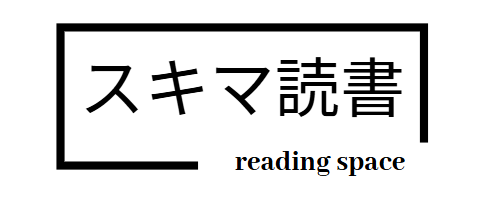


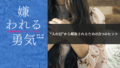
コメント